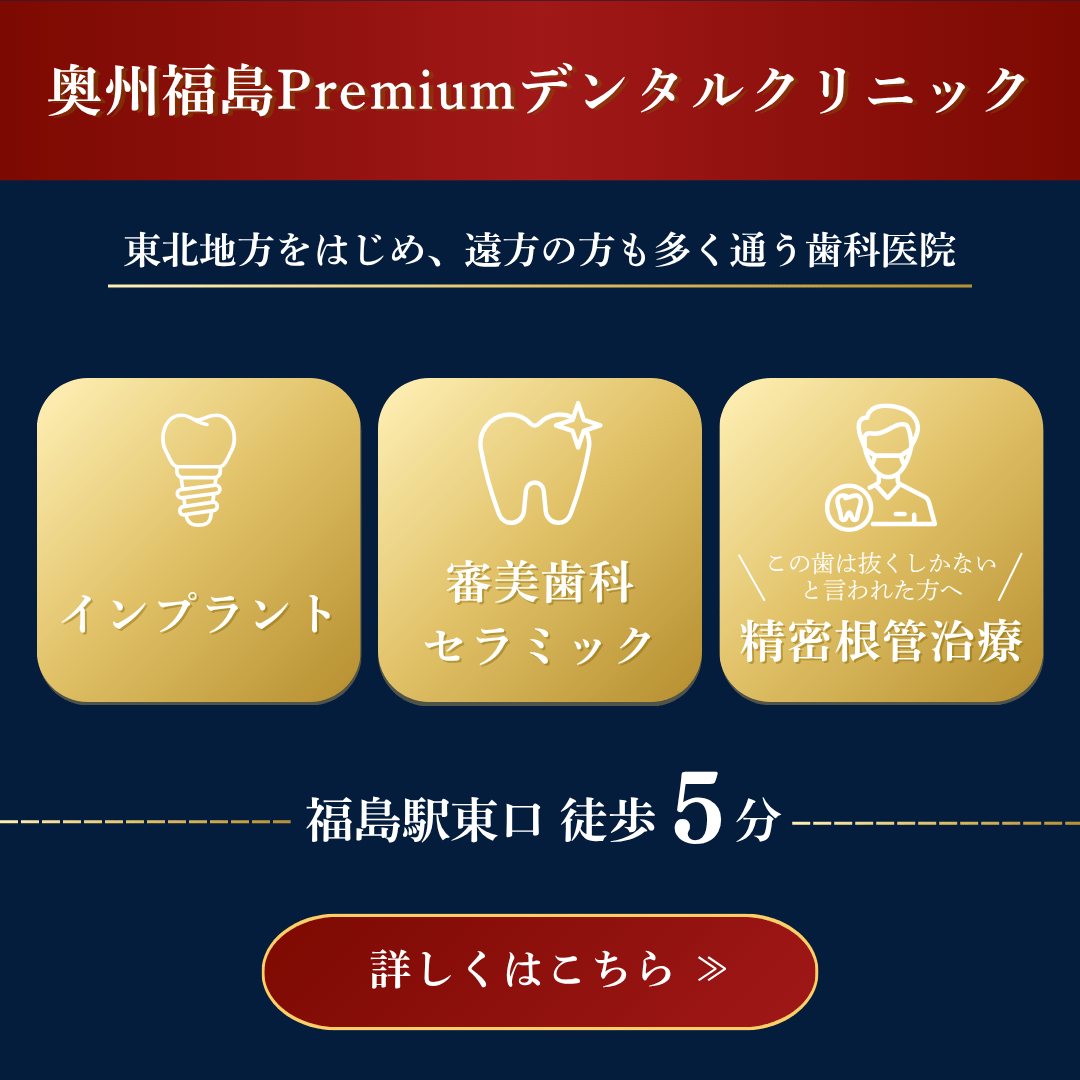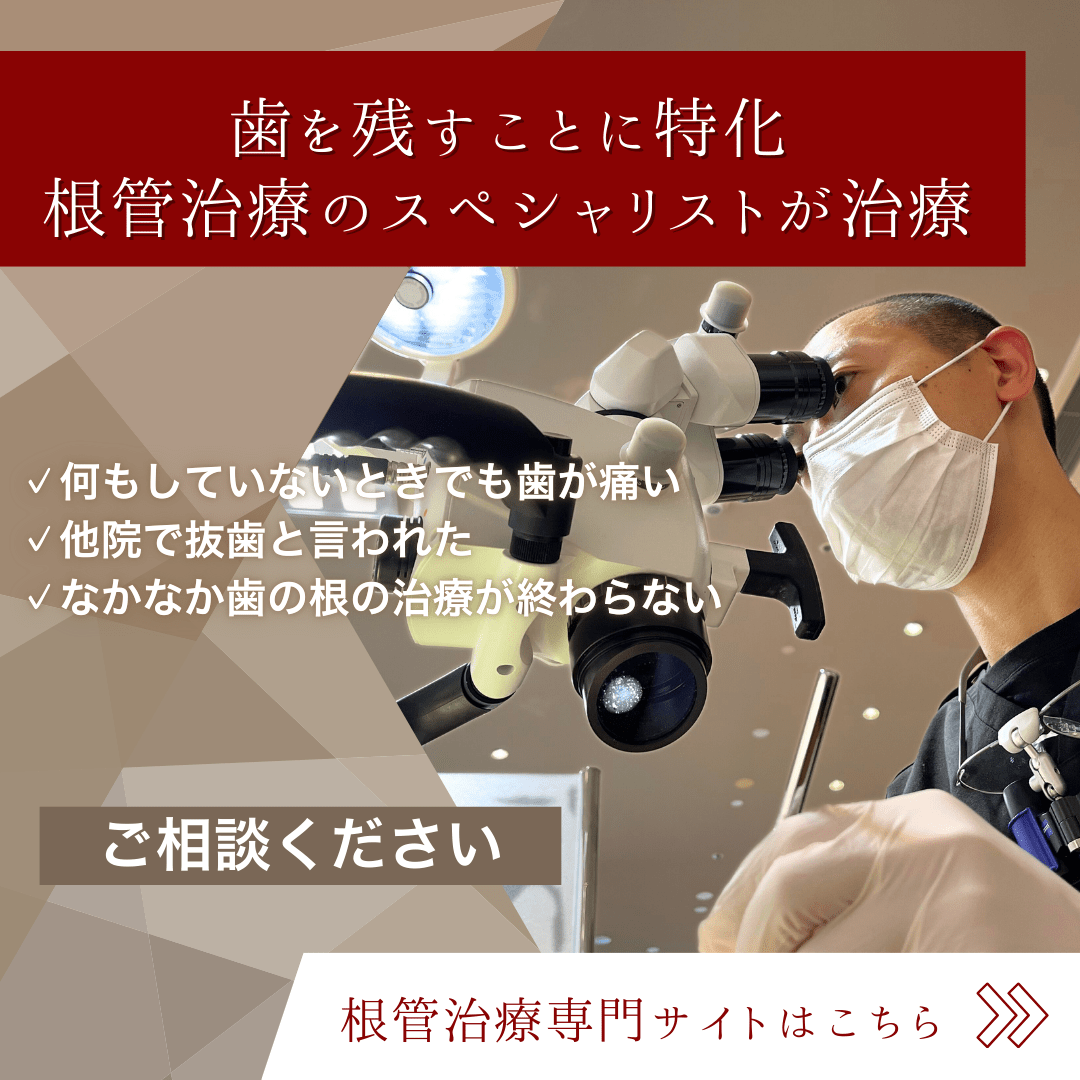▼目次
1. 根管治療中の歯磨きはどうすればいい?
2.痛みや違和感があるときの歯磨きのコツ
3. 根管治療中のトラブルを防ぐための歯ブラシ選びで気を付けること
4. 福島駅東口すぐの歯医者 奥州福島Premiumデンタルクリニックの根管治療
まとめ
根管治療は、むし歯が神経まで進行してしまった場合に行われる治療で、治療期間が長引くこともあります。その間に気になるのが、「歯磨きはどうすればよいのか」という点ではないでしょうか。痛みがある中での歯磨きや、治療中の歯をどのように扱えばよいのか、不安に感じる方も少なくありません。今回は、根管治療中の歯磨きの方法や注意点について、福島駅東口すぐの歯医者 奥州福島Premiumデンタルクリニックが解説します。
1. 根管治療中の歯磨きはどうすればいい?
根管治療中でも、口の中を清潔に保つことはとても大切です。特に、治療中の歯や周囲の歯ぐきをきれいに保つことで、感染リスクに配慮したケアにつながります。
①治療中の歯も丁寧に磨く
治療中の歯も、通常は磨くことが推奨されます。ただし、強くこすらず、優しく当てるように意識しましょう。痛みや出血がある場合は無理をせず、歯科医師の指示に従ってください。
➁歯ブラシの毛先をしっかり管理する
毛先が開いた歯ブラシでは歯垢(プラーク)が落ちにくく、歯ぐきを傷つけるおそれがあります。1か月を目安に、新しい歯ブラシへ交換するようにしましょう。
③うがいで清潔を保つ
痛みが強く、どうしても歯ブラシが当てられないときは、うがいで対応しましょう。水や薄めた洗口液を使い、食後にていねいに口をすすぐだけでも、清潔を保つのに役立ちます。
④フロスや歯間ブラシの使用に注意
根管治療中は歯と歯の間に汚れがたまりやすいため、フロスや歯間ブラシが有効です。ただし、治療中の歯に強く触れないよう注意が必要です。
⑤歯科医師の指示を優先する
自分で判断せず、処置後の注意点を守りながらケアを行うことが大切です。治療の進行状況によっては歯磨きの方法を調整する必要があるため、定期的に相談しましょう。
根管治療中でも口の中を清潔に保つことは欠かせません。無理のない方法でケアを続けることが、よりよい治療経過につながります。
2.痛みや違和感があるときの歯磨きのコツ
根管治療中は、処置後に数日ほど歯や歯ぐきが敏感になることがあります。こうした時期の歯磨きは無理に行わず、状況に応じてケア方法を変えることが大切です。ここでは、痛みを感じるときに意識したいポイントをまとめます。
①やわらかいタッチで磨く
痛みがあるときは、歯ブラシを強く当てるほど刺激が大きくなります。力を入れず、毛先をそっと触れる程度で磨くことを意識しましょう。
②無理に治療部位へ触れない
痛みが強いときは治療中の歯に歯ブラシが当たると症状が悪化する可能性があります。その場合は無理に磨かず、周囲の歯だけケアする方法もあります。
③洗口で清潔を保つ
ブラシが当たるのが難しいときは、うがいで汚れを落とします。水や薄めた洗口液を使うことで、口の中をすっきりさせることができます。
④温度刺激を避ける
冷たい水がしみることがあるため、歯磨きやうがいには常温の水を使うと刺激を抑えやすくなります。
⑤症状が続く場合は相談する
痛みが長引く場合や磨けない日が続く場合は、自己判断せず歯科医師に相談し、状態に合ったケア方法を確認することが大切です。
痛みがあるときは「無理に磨かず、できる範囲で清潔を保つ」ことが基本です。負担を避けながらケアを続けることで、治療を円滑に進めやすくなります。
3. 根管治療中のトラブルを防ぐための歯ブラシ選びで気を付けること
治療中の歯はデリケートになりやすいため、どの歯ブラシを使うか、どのようなケア用品を選ぶかが大切です。ここでは、痛みの有無に関わらず治療中に役立つ道具選びのポイントを紹介します。
①ヘッドの小さい歯ブラシを選ぶ
小さめのヘッドは細かい部分まで届きやすく、治療中の歯に負担をかけずに磨くことができます。奥歯や治療部位の周囲にも当てやすい形状です。
②毛の硬さは「やわらかめ」を選ぶ
やわらかい毛は歯ぐきや治療中の部分への負担を抑え、炎症がある場所にも当てやすい特徴があります。
③タフトブラシを補助として使う
タフトブラシは、部分的に汚れが残りやすい場所へピンポイントで届くため、通常の歯ブラシと併用することで清掃性を高めやすくなります。
④刺激の少ない歯みがき粉を選ぶ
発泡剤や研磨剤が控えめなタイプは、治療部位に刺激を与えにくいためおすすめです。メントールの強いものはしみる場合があるため注意が必要です。
⑤洗口液で仕上げのケアを行う
ブラッシングだけでは落としきれない汚れに対して、洗口液を併用すると清潔を保ちやすくなります。刺激が少ないタイプを選ぶことが大切です。
道具選びやケア用品を見直すことで、治療期間中でも口の中を清潔に保ちやすくなり、トラブルの予防にもつながります。
4. 福島駅東口すぐの歯医者 奥州福島Premiumデンタルクリニックの根管治療
福島市・福島駅東口の歯医者 奥州福島Premiumデンタルクリニックは、歯を残すことに特化した根管治療を提供しています。マイクロスコープを用いた精密治療で患者さんの大切な歯を守ります。
歯を残すためには今ある歯を正しく診査・診断した上で治療方針を決定する必要があります。そのためには治療前にレントゲン・CT撮影や口腔内の温痛、冷通、打診痛などの検査、患者さんご自身からのヒアリングなど診査・診断を丁寧に行います。その結果を元に患者さんの生涯のお口の健康を考えた治療法を提案いたします。
また、根管治療を成功に導くためには歯と歯周組織に細菌感染が再び起こらない環境で治療を行う必要があります。そのために器具は滅菌済みや使い捨て(新品)を使用し、ラバーダムという特殊なゴムで唾液による細菌感染を防ぐなど「無菌的環境下」で治療を行うことも大切です。
「かかりつけの歯科医院で抜歯が必要と言われた」「歯の根の治療(根管治療)を何回も繰り返している」「治療後に歯や歯茎にずっと違和感がある」など、自分のお口に不安がある方は是非一度奥州福島Premiumデンタルクリニックにご相談ください。
▼詳細はこちらのページから
まとめ
根管治療中の歯磨きは、治療をスムーズに進めるための大切なケアのひとつです。痛みや違和感がある場合でも、無理のない範囲で適切に歯を磨き、口の中を清潔に保つことが求められます。やわらかめの歯ブラシやタフトブラシの併用、刺激の少ないケア用品の選択、そして歯科医師への相談を心がけましょう。
根管治療中の歯磨きについてお悩みの方は、福島駅東口すぐの歯医者 奥州福島Premiumデンタルクリニックまでお問い合わせください。
監修
院長・審美歯科担当 山田 恵理