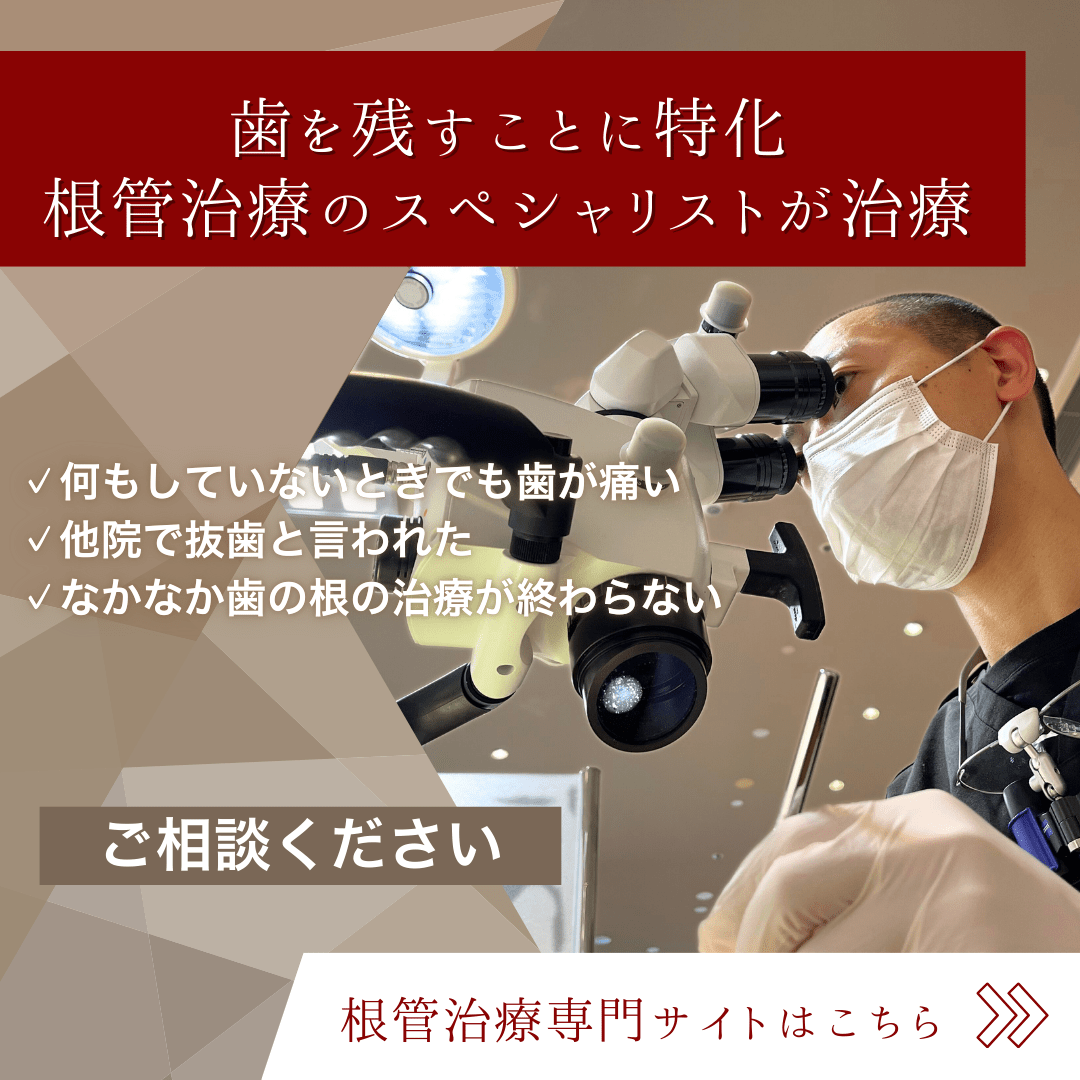▼目次
歯がズキズキと痛む、冷たいものや温かいものがしみる――そんな症状が続く場合、「歯髄炎(しずいえん)」の可能性があります。歯髄炎とは、歯の内部にある神経(歯髄)が炎症を起こしている状態を指します。むし歯が進行すると発症しやすく、放っておくと痛みが悪化したり、歯を失う原因になることもあるため、早期の対応が重要です。今回は、歯髄炎の原因や症状、治療方法、通院の流れについて解説します。
1. 歯髄炎とは?虫歯との違いと炎症が起こる仕組み
歯髄炎は、歯の内部にある歯髄という組織に炎症が生じた状態を指します。歯髄には血管や神経が通っており、歯に栄養や感覚を与える重要な役割を果たしています。この部分に炎症が起こると、強い痛みやズキズキとした違和感が現れることがあります。
① 歯髄炎とむし歯の違い
むし歯は歯の表面(エナメル質や象牙質)に起こる病気で、初期段階では痛みが出ないこともあります。一方、歯髄炎はむし歯が進行して神経にまで達し、歯髄が炎症を起こした状態です。つまり、むし歯の「末期症状」の一つといえます。
➁ 歯髄炎の原因
・むし歯の進行による細菌感染
・歯に強い衝撃や外傷を受けた場合
・過去の治療で神経に近い部分が刺激を受けた場合
・歯周病の悪化によって歯の根から感染が広がるケースもある
➂ 歯髄炎が起こる仕組み
むし歯などによって歯の内部に細菌が侵入すると、歯髄が感染し炎症を起こします。これにより血流が増し、神経が圧迫されて痛みが強まります。炎症が進行すると、歯髄は壊死し、やがて細菌が歯の根やあごの骨にまで広がる恐れがあります。
➃ 急性と慢性の違い
・急性歯髄炎:突然の激しい痛みが特徴。何もしなくてもズキズキと痛むことがある。
・慢性歯髄炎:痛みは軽減しているが、歯髄がすでに死んでいる状態。無症状でも進行している可能性がある。
➄ 自然に治ることはない
歯髄炎は一度起こると、自然に治ることはありません。痛みが治まっても炎症が進行していることが多く、早期の治療が必要です。
歯髄炎はむし歯と密接な関係があり、放置することで状態が悪化するため、「いつもと違う痛み」を感じたら早めに歯科医院を受診することが重要です。
2.歯髄炎の治療法
歯髄炎の治療は、炎症の程度や歯の状態によって異なります。歯髄を残せるかどうかが治療法の大きな分かれ道となります。ここでは、主な治療法について説明します。
①歯髄温存療法
《治療の特徴》
歯髄温存療法は、虫歯や外傷などで歯の神経(歯髄)が刺激を受けているものの、まだ完全には死んでいない場合に行われる治療です。神経を残すことで、歯本来の感覚や血流を保ち、歯の寿命を延ばすことを目的としています。軽度の歯髄炎や一部の神経のみが炎症を起こしている場合に適用されます。
《治療の流れ》
まず虫歯を丁寧に取り除き、歯髄が露出している部分に適切な薬剤(水酸化カルシウムやMTAなど)を使用して、歯髄の炎症を抑えます。その上から仮の詰め物で封鎖し、経過を観察します。問題がなければ最終的な修復(詰め物や被せ物)を行います。
《リスク・注意点》
治療後も炎症が続く場合や、痛みが再発するケースがあります。その場合は抜髄が必要になることもあります。また、治療の成否は歯髄の炎症の程度によって左右されやすく、判断には歯科医の的確な診断が求められます。治療後の定期的な経過観察が重要です。
②抜髄
《治療の特徴》
抜髄は、歯髄の炎症が強く、自然治癒が見込めない場合に行われる治療です。歯の神経や血管を取り除くことで痛みや炎症を解消し、歯を残すことが目的です。強い自発痛がある場合や、歯髄が感染している場合に選択されます。
《治療の流れ》
治療はまず局所麻酔を行い、虫歯部分とともに歯髄を除去します。その後、歯の内部(根管)を洗浄・消毒し、無菌状態に保つために根管充填材で密閉します。複数回に分けて治療が行われることが多く、最終的には被せ物などで歯を補強します。
《リスク・注意点》
神経を取ることで歯は痛みを感じなくなりますが、その分脆くなり、割れやすくなるリスクがあります。また、根管内に細菌が残ると再感染する可能性があり、治療後も継続的な管理が求められます。根管の形状が複雑な場合は治療が難航することもあります。
3.歯髄炎を放置するリスク
歯髄炎は放置すると自然に治ることはなく、症状が進行するほど歯や全身への悪影響が大きくなります。ここでは、歯髄炎をそのままにした場合に起こり得るリスクについて解説します。
① 神経が壊死して痛みが消える=治ったわけではない
歯髄炎が進行すると、神経が壊死して痛みを感じなくなることがあります。一見「痛くないから治った」と思いがちですが、実際には内部で細菌が増殖し続けており、より深刻な状態へと進行していることが多いです。
➁ 根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)への移行
壊死した神経が放置されると、根の先から細菌が漏れ出して歯の根の周囲に炎症が広がり、根尖性歯周炎という状態になります。噛むと痛い、歯ぐきが腫れる、膿が出るなどの症状が現れ、さらに治療が難しくなります。
➂ 歯の破折や抜歯が必要になるケースも
根管治療が遅れると、歯の構造が弱くなり、歯根が割れてしまうことがあります。歯根が割れると、保存は難しくなり、抜歯を選択せざるを得ないこともあります。歯を残すためには、できるだけ早い治療が不可欠です。
➃ 骨や他の組織への感染拡大
感染が進むと、顎の骨や頬、場合によっては全身にまで炎症が広がることがあります。重症化すると入院や点滴治療が必要になるケースもあり、歯の病気とはいえ軽視できません。
➄ 口臭や膿が出るなどの生活への影響
根の先に膿がたまると、口臭の原因になったり、歯ぐきから膿が出てくることがあります。見た目や衛生面にも影響を与えるため、日常生活の質を損なうことにもつながります。
➅ 周囲の歯や噛み合わせへの悪影響
歯髄炎で治療せずに抜歯に至った場合、失った歯をそのままにすると、隣の歯が動いたり噛み合わせがずれたりするリスクがあります。結果的に、他の健康な歯にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このように、歯髄炎を放置することで、さまざまなトラブルが生じます。歯や口の中の健康だけでなく、全身の健康にも関わる可能性があるため、痛みが出たら放置せず、早めに治療を受けることが大切です。
4. 奥州福島Premiumデンタルクリニックの根管治療について
奥州福島Premiumデンタルクリニックは、歯を残すことに特化した根管治療を提供しています。マイクロスコープを用いた精密治療で患者さんの大切な歯を守ります。
歯を残すためには今ある歯を正しく診査・診断した上で治療方針を決定する必要があります。そのためには治療前にレントゲン・CT撮影や口腔内の温痛、冷通、打診痛などの検査、患者さんご自身からのヒアリングなど診査・診断を丁寧に行います。その結果を元に患者さんの生涯のお口の健康を考えた治療法を提案いたします。
また、根管治療を成功に導くためには歯と歯周組織に細菌感染が再び起こらない環境で治療を行う必要があります。そのために器具は滅菌済みや使い捨て(新品)を使用し、ラバーダムという特殊なゴムで唾液による細菌感染を防ぐなど「無菌的環境下」で治療を行うことも大切です。
「かかりつけの歯科医院で抜歯が必要と言われた」「歯の根の治療(根管治療)を何回も繰り返している」「治療後に歯や歯茎にずっと違和感がある」など、自分のお口に不安がある方は奥州福島Premiumデンタルクリニックにご相談ください。
まとめ
歯髄炎は、むし歯の進行によって神経に炎症が起こる状態で、放置すれば歯を失うリスクが高まります。初期段階では神経を残せることもありますが、炎症が進むと抜髄や根管治療が必要となります。痛みが一時的に引いたとしても、内部では感染が進行している可能性があるため、早めの受診が重要です。歯髄炎を正しく理解し、適切な対応を取ることで、自分の歯を長く健康に保つことができます。
福島市で歯髄炎やむし歯の進行にお悩みの方は、ぜひ福島駅東口からすぐの歯医者 奥州福島Premiumデンタルクリニックまでお気軽にご相談ください。
監修
奥州福島Premiumデンタルクリニック
TOKU根管治療専門室 鈴木篤太郎